「重い荷物を運んでいたらぎっくり腰になった」「長いこと慢性的な腰痛に苦しんでいる」
厚労省のデータで見ても、腰痛で悩んでいる方は国内で2800万人を超えると言われており、私達の身近な病気になっています。
そんな患者数の多い腰痛の対処法として、多くの方が使用しているのが湿布薬です。
最近では、ドラッグストアなどでも様々な種類の湿布薬が販売されており、どれを購入していいか迷ってしまう方もいると思います。
結果から先にお話すると、「急性腰痛には冷湿布系」を「慢性腰痛には温湿布系」の貼付剤を使用することが効果的です。
自分の腰痛が「急性腰痛なのか?慢性腰痛なのか?」と正しく理解して湿布を使い分けましょう。
そこで、今回は腰痛の種類(急性期と慢性期)による湿布薬の使い分けと注意点について薬剤師の観点から紹介します。
ご自身で湿布薬を購入する際の参考にしてもらえれば幸いです。
目次
腰痛で使う湿布薬の種類と特徴
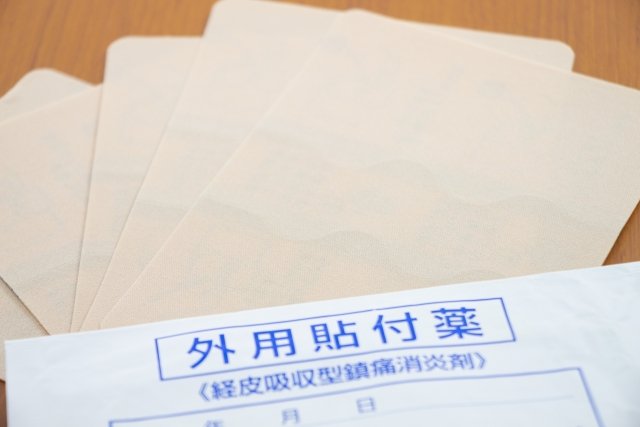
私達が普段、病院やドラッグストアなどで入手する湿布は「経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤」という成分を配合した貼付剤のことを指します。簡単に説明すると、皮膚から痛みや炎症を和らげる成分を吸収して効果を発揮するものです。
そして、湿布は大別すると冷湿布と温湿布の2種類に分けられます。
まずは、それぞれ特徴をみていきましょう。
冷湿布の特徴
冷湿布は、主要な効果として炎症や痛みを和らげる目的で使われます。
冷却成分として、カンフルやメントールなどの成分を使用しており、熱をもっている患部を冷やして急性期の症状などに効果がでるようにしています。
しかし、冷湿布による冷えは実際に患部を冷やしているわけではありません。
メントールなどの成分が、皮膚の感覚の違いを出して、脳に痛みを感じにくくさせています。
ですから、捻挫などアイシング目的で使用するときは、湿布だけでなくアイスパックなどもオススメです。
温湿布の特徴
温湿布は、主要な効果として血流の改善目的で使用されます。
温感成分として、カプサイシンなどのトウガラシエキスを含有しており、温感作用による血流改善で慢性の腰痛などに効果がでるようにしています。
また、温湿布も冷湿布同様に患部を実際に温めているわけではなく、皮膚をポカポカと感じるようにしているだけです。
冷湿布と同じように、温める効果としてはホットパックなどを使うといいでしょう。
湿布素材による使い分け
湿布はその成分から痛みや炎症を和らげる目的で使用されますが、患部の場所や肌質に応じて素材を使い分ける必要があります。
湿布の素材は、「パップ剤」と「テープ剤(プラスター剤)」に分けられます。
こちらも特徴と使い分けを見ていきましょう。
パップ剤の特徴
パップ剤とは、水分を多く含むジェル状の軟膏を布やプラスチックフィルムに貼り付けたものをいいます。
水分を多く含むため、肌に優しい素材にはなっており、冷えを感じやすくなっていますが、はがれやすいという欠点もあります。
そのため、パップ剤を使う場合は、首や肩などの皮膚の弱い部分で使用したり、ネットや包帯などで固定してあげると使いやすいでしょう。
テープ剤(プラスター剤)の特徴
テープ剤(プラスター剤)は、薬効成分と粘着剤を混ぜ合わせたものをポリエチレンフィルムなどに薄くのばした貼付剤になります。TVCMなどでお馴染みの「ロキソニンテープ」など様々な種類のものが販売しています。
パップ剤に比べると、粘着性が高いのではがれにくく違和感も目立ちません。
また、伸びもいいので、肘や膝などの関節部には動いてもはがれないためオススメです。
しかし、こちらは粘着性が強力なため、はがすときの痛みやかぶれ症状などがパップ剤に比べると多くなってしまう欠点もあります。
腰痛症状での湿布の効果的な使い方
では実際に、腰痛で湿布を使用する際の効果的な使い分けについて紹介します。
最初にもお話しましたが、腰痛の湿布の使い分けには急性腰痛と慢性腰痛の2種類に分けて考えることが重要です。
急性腰痛症での湿布治療
急性腰痛とは、一般的に「ぎっくり腰」と呼ばれるものを指します。
重い荷物を持ち上げたり、腰をひねるような動作をした際に、突然腰痛を発症して動けなくなるような症状のことです。原因としては、腰部椎間板(ようぶついかんばん)の断裂やヘルニアなどが考えられます。
湿布の選択としては、急性腰痛症は痛みが強く炎症が起こっている状態です。
はじめにも説明しましたが、湿布は冷湿布を選ぶようにしましょう。
温湿布などで温めると炎症には逆効果になるため注意してください。
また、急性腰痛では冷湿布以外にも痛みを抑えるため、内服の鎮痛薬などで処置することがあります。
基本的には安静にしておくことで2.3日~1週間程度で治ることがほとんどです。
ぎっくり腰におすすめの湿布
ぎっくり腰などの急な痛みに対しては、強めの成分が良いと言われています。
ロキソプロフェン・ジクロフェナクナトリウム・フェルビナクが含まれている湿布を選んでみましょう。ただし、ぎっくり腰には色々な原因があるので、場合によっては効果を感じにくい場合があります。
慢性腰痛症での湿布治療
慢性腰痛症とは、原因はどんなことであれ発症から3ヶ月以上続く腰痛症のことを指します。
腰部椎間板ヘルニアや変形性脊椎症、骨粗鬆症など様々なことが原因になりますが、痛みが長期におよび、精神的な要素も悪化の要因になりえます。
急性腰痛とは比べると、動けないほどの痛みではなく炎症も強くはありません。
また慢性腰痛症では、動作自体がめんどうになっている方が多く、血流が滞っていて症状が悪化している場合もあります。
そこで、湿布薬は温湿布を使用して、腰回りの血流を改善させてあげることが効果的です。
ただ、慢性腰痛症では冷湿布を使用することがダメなわけではないので、急性腰痛と違って個人の好みで使い分けてもいいと思います。
他にも、ストレッチや認知行動療法など安静にしておくよりも、動いていた方が症状の治りが早いことも分かっています。
湿布で起こりうる副作用と注意点

最後に、腰痛症などで湿布を使う際に起こりえる副作用と注意点について紹介します。
ネットやドラッグストアなどで湿布を購入している方は下記のことに注意して使用してください。
湿布の貼付時間
よく薬局などで患者さんから話を聞くと、24時間効果がでる湿布薬を1日中貼ったまま使用している方がいらっしゃいます。
しかし、この使い方は間違いです。
湿布薬は経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤という名前からも分かる通り、皮膚から痛みに効く成分を吸収して効果を発揮します。その効果時間は、1日1回の湿布なら基本的には24時間持続しますが、皮膚からお薬の成分を吸収する時間は8~10時間ほどで終わってしまいます。
ですから、1日1回の湿布では8~10時間ほど貼ってはがしても、痛み止めの効果は1日中持続するようになっています。
長時間貼り続けることで、成分吸収において意味がないだけではなく、皮膚炎やかぶれなどの副作用リスクを上昇させる要因にもなるので注意しておきましょう。
貼付時間の目安
・1日1回貼付剤の場合→8~10時間ほど
・1日2回貼付剤の場合→4~6時間ほど
光線過敏症
湿布剤を使用していて注意しないといけない副作用に光線過敏症があります。
光線過敏症とは、光を浴びることで皮膚が赤くなって、かゆみなどを生じるものです。
これは、「ケトプロフェンテープ」などで起こりやすいことが分かっているもので、湿布をはがしていても起こることが分かっています。
対策方法としては、長袖などで湿布を貼っていた部分への直射日光を避けることやロキソニンテープなど比較的光線過敏症が起こりにくい湿布薬への変更を検討するといいでしょう。
湿布を用いるタイミング
腰痛の症状が出るということは、腰で何らかの異常が起こっているという警告であるとともに、何らかの異常で傷ついた組織を修復しようとする反応(炎症)が起こりはじめたという合図でもあります。
傷ついた組織を修復しようとする反応が起こると、腰へ流れ込む血流量は次第に増えていき、その結果、腰では赤みや腫れ、熱感、痛みといった症状が強く見られるようになってきます。
そのため、このタイミングで『湿布』を用いることが、この反応で反動的にもたらされるカラダへの負担を軽減し、組織の修復を速やかに終わらせて『治癒』へとスムーズに移行させる手助けとなるのです。
だからといって、むやみに『湿布』を使用し続けると、いつまでたっても組織の修復が終わらず、治癒を遅らせてしまう可能性もあるため、さらなる症状の継続や悪化を引き起こしかねません。
『湿布』はあくまで「腰痛の症状を軽減させる」ものであり「腰痛そのものを根本から治す」ものではありません。
腰痛の症状が出たタイミングに合わせて使用し、常に用法・用量を正しく守ることを心がけましょう。
まとめ
腰痛症での湿布の使い分けについて紹介してきましたが、湿布はあくまで痛みを抑える補助的な目的で使用するものです。
記事で紹介したような副作用などの症状に気を付けて、しっかりと使い分けることが大事になります。
どうしても腰痛症状が改善せず長引く場合は一度専門医への相談してみるといいでしょう。














